ひと作品読み終えたのでまた感想文を書く。
今回読んだのはこちら

まず最初に述べておこう。
「今まで読んだことが無かった村上春樹作品を読んでみたいけど何読んだらいいかわからない」と悩むそこのあなた。
大人しく『一人称単数』を読みなさい。
『ノルウェイの森』のような初心者向けとか人気作品といったネットの情報は間に受けず、手っ取り早く読める短編作品である『一人称単数』が断然オススメだ。
まあ、僕は読んだことはないけど。
はじめに
僕の知る村上春樹さんといえば、“名前は聞いたことはあるが、どんな本を書いたのか知らない人”であり、「やれやれ。僕は〜」の人だ。要するにネットで見かけたら知らん人である。
人生何があるかわからないし、もしかすると明日突然何かの拍子に乗ってる車が爆発して死ぬかもしれない。生きているうちに有名作家の作品をかじっておきたい。そう思い至り、最近著者6年ぶりの発刊された最新長編『街とその不確かな壁』でお馴染みの村上春樹さんに目をつけた訳だ。彼がこれまで送り出した数ある著書の中でも、ネットでおすすめされていた 『ノルウェイの森』を手に取ってみた。
さて、自分語りはこの辺りとして、以下に作品の簡単なあらすじと感想をを述べることとする。
あらすじ
「やれやれ、またドイツか」
37歳のワタナベ トオルは、心の中で呟いた。
彼の乗るドイツ行きの飛行機は、ほどなくしてハンブルク空港に着陸した。降機までの間、機内ではBGMとしてビートルズの『ノルウェイの森』が小さな音で流れる。そのBGMは、ワタナベの情緒を激しく揺さぶると共に、自身を縛るかつての記憶を呼び起こしたーー。
大学生時代、ワタナベは亡くなった親友の居た町を離れ、東京の学生寮に住んでいた。親友の名はキズキ。キズキには直子という恋人が居て、ワタナベは2人のことが大好きでよく遊んでるいた。しかし、キズキの突然の訃報により、ワタナベのなかで生と死の観念が変わった。
無難な大学生活を過ごすある日のこと、偶然にも東京の地でキズキの恋人だった直子と再会する。直子もまた、キズキの死と共に何かが変わってしまった。
去し者と残された者。
求める者と求めざる者。
ワタナベの記憶から喪失の1969年が振り返られる。
感想

率直に、且つ簡潔に感想を申し上げると「難しかった」の一言に尽きる。
知らない時代。知らない大学生活の風景。知らないミュージシャンの楽曲。共感する部分を探そうにも、共感出来そうな部分が中々見当たらない。そもそも時代が60年代後半な時点で平成育ちの僕はもう着いていけない。しかも、物語はワタナベが淡々と日々を過ごすだけのものである。何かが始まりそうな気がして、別に物語が予想外な急展開に入ったりするなんてこともない。共感性が薄いし、物語に抑揚がない。正直な話、読んでてものすごく退屈だった。
それに、何よりもあのスケベ場面だ。そう、さも当然であるかのように、事あるごとにおせっせを押っ始めるあれだ。なんの予備知識の無いままそれらの場面を読んだ時は、それはもう驚いたものだ。あの極自然な導入。どこかねっとりとした生々しさ。どこか乾いている世界観とのギャップ。こういった場面が苦手だという人もそれなりに居るだろうに、この作品が万人に受け入れられているのが信じられない。正に酒!音楽!S◯X!である。(後にネットで調べてわかったが、このネチネチした濡れ場こそが村上春樹作品らしさとの事)
ただまあ、純文学作品ってのは大抵がそんな物なのかもしれない。良く言って“詩的”、悪く言って“独善的”な文章も、見方によれば芸術的に見えるような気がする。それに、著者の思想と世界観がそのまま描かれたかの様な作品、と言われればまあ納得出来る。村上春樹自身も60年代をワタナベのようにウィスキーを片手にレコードで洋楽を聴いていたことだろう。でなければ、当時を知らない僕でも分かる様な克明な情景を文章化できるはずがない。
それに読み進めていると、少しではあるが共感できそうな部分は見つかったし、心が揺さぶられるような刺さる言葉も発見した。
例えば、ワタナベが直子に向けて何通も手紙を送る行動とか共感の塊だ。直子と寝た後のワタナベは、連絡の取れなくなった直子に向けて2度に渡り長文の手紙を送る。この場面に、未練と性欲に満ちた男臭さを感じる。男ならば、誰だってワンチャンス感じてしまった娘に未練たらしくメッセージを送ってしまうものだし、ついつい行動原理が性欲に支配されることはあるものだ。なんだか鏡に映る自分を見ているようで非常に気持ち悪い。
「心を揺さぶられるような刺さる言葉」を以下に挙げてみる。
死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。
出典:村上春樹.ノルウェイの森(上).講談社.講談社文庫.2004.P54
キズキの死によってワタナベが見出した考え。月並みな死生観よりも深く心に残った一文だ。生と死は全く別の存在で、それぞれが隣り合わせに位置しているのではない。死は生の一部であり、別存在だと思った死はいつだって生の中に存在する。そう考えると、急に生に対する危機感が湧き上がってくるような気がした。
「自分に同情するのは下劣な人間のやることだ」
出典:村上春樹.ノルウェイの森(下).講談社.講談社文庫.2004.P189
ワタナベの住んでいた寮の先輩・永沢が、寮を出て一軒家に住むことになったワタナベに向けて贈った忠告。上手くいかなくなった時。自暴自棄になった時。失敗して自分を卑下してしまいそうな時。自分を守るための考えとして脳に刻んでおきたい台詞。
まとめ
まあ、難解ではあったが、どこか引き込まれてしまうような深みと魅力のある作品だった。
本来ならこの作品について深く考察すればよいのだろうが、今更そんなことをしたって十番煎じにもならない。が、一応僕なりに思い至った作品タイトルについての考察を残しておく。
・「森」とは、立ち行かぬ愛に翻弄される精神のメタファー。愛と一言で表してはみたが、恋愛のように甘く切ない愛でもなければ、愛憎のように憎しみに満ちた愛でもない。どこか、カラカラと乾いた殻の中にネチネチと湿った塊があるような煩雑さが感じられる。ワタナベと直子は、キズキを失った時点で「森」に囚われており、直子は死を持って森を抜け出したが、ワタナベは直子を失ったことで更に深くに囚われる。17年経った物語冒頭の時代においても、尚彷徨い続けている。また、もう1人のヒロイン・緑も「森」に囚われている者の1人であった。ヤングケアラーとして家族に縛られていたり、彼氏が居ながらワタナベへの想いに囚われていたりと、ワタナベとは違うようで似ている森に迷い込んでいたのではないだろうか。
さらにここで村上春樹作品初心者らしく、春樹作品を読む前と後での印象の変化も書き残しておく。
読前
・やれやれ、僕は射精した(偏見)
↓
読後
・やれやれ、僕はレコードを聴きながらウィスキーを飲み、そして射精した

以上、ありがとうございました。
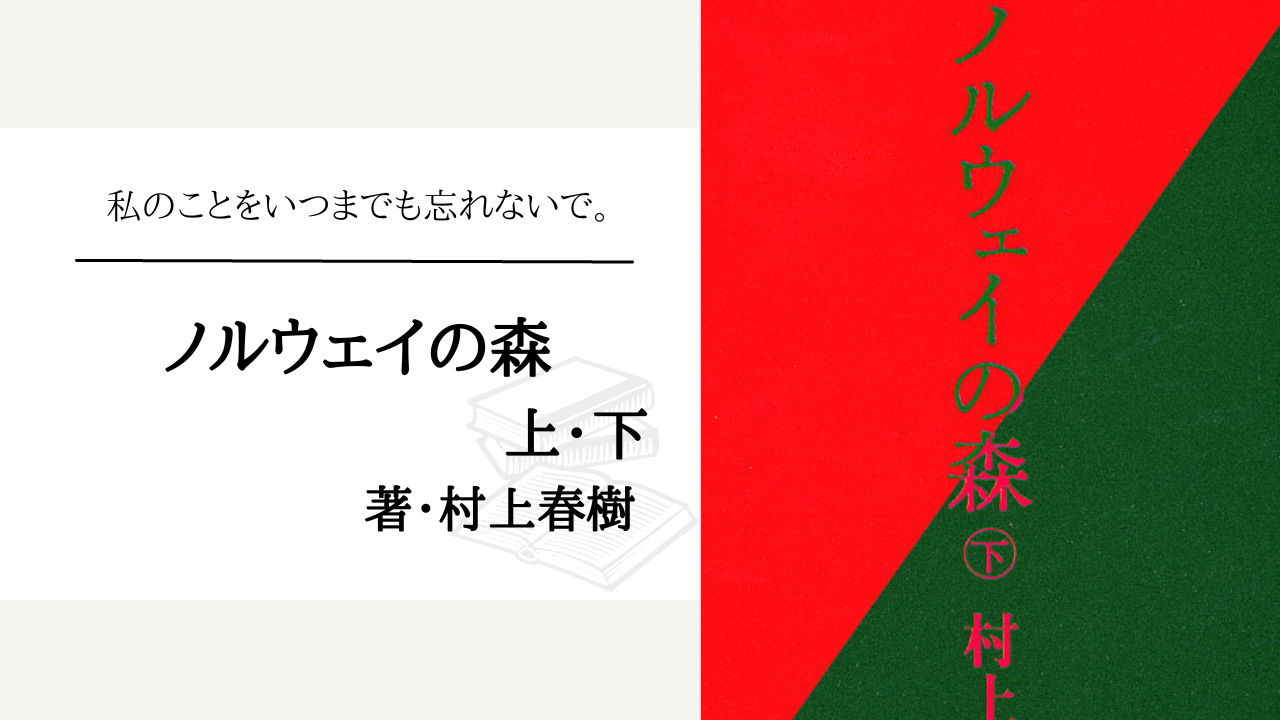


コメント